人事戦略・組織活性化Activation
モチベーションアップのための組織作り
人は声かけで変わる。変わるのは経営トップ
人は誰しも認められたい、適正に評価してほしいと願っているはずですが、それをうまく表現できないのが日本人であるといえます。よく自己実現の欲求に関して引き合いに出されるのが、A・マズローの欲求階層説です。
- 自己実現の欲求 (Self-actualization)
- 尊厳の欲求 (Esteem)
- 社会的欲求 / 所属と愛の欲求 (Social needs / Love and belonging)
- 安全の欲求 (Safety needs)
- 生理的欲求 (Physiological needs)
低次の欲求が満たされると、その上の欲求が満たされるように動き、最終的には自己実現という形で表されるというもの。これが全てはありませんが、考え方として代表される学説です。ここに、「承認」欲求が入るとも言われています。自己実現に近づくとともに、認められる、承認される意識が芽生えてきます。そこを、経営者の皆様や管理監督者、あるいは同僚でもそうですが、一つ上のステップに上がるためには、どの段階においても「承認」は必要になります。組織を見渡して、お互いがお互いを認め合う意識が持てているとしたら、その組織は強くなると考えます。
ぜひ、組織活性化の見直しをしていきましょう。

組織活性化のポイント
- ポイント1従業員ヒアリングを行うことで、溜まったものをデトックス
- よく、従業員満足度調査をやっていますが、毎年おざなりになってしまっていて、今ひとつ効果が感じられないという声を聞きます。いくら調査をやっても、実態が反映されていないものは、答えている従業員も辛いもの。実態に近づけるためには、みなさんの声を聞くことが手っ取り早いです。ぜひ、外部のヒアリングを行ってみませんか。
- ポイント2承認というテーマで組織を見渡してみる
- 同志社大学の太田肇先生は、承認のテーマで何冊もの著書と研究を発表しています。先にも述べましたが、日本人は褒められること、認められることに慣れていません。そこで、「ありがとう」とか「助かったよ」など、ちょっとの言葉から相手を認めることからはじめてみることも大切です。お互いに少しずつの歩み寄りもいい環境になります。
- ポイント3適正な評価制度で、本人にフィードバック
- 大企業だけでなく、中小企業でも評価制度は必要ですが、大企業でもできていないのが評価制度の運用です。制度の運用が一番難しいこともあり、後回しになっている感は否定できません。でも、これをきちんとフィードバックされるのを従業員は期待していますので、経営面でも適正に運用したいものです。
組織と人の成長を最大化して、企業の未来を拓く

- 人事制度構築・見直し
- 理念・目標実現に不可欠な、最適解となる人事制度をデザイン。企業の成長戦略に合わせ、等級・評価・報酬制度などを設計・見直し、導入から運用までを丁寧にサポートします。組織の活性化と従業員のモチベーション向上を通じて、目標達成を人事の側面から全力で支援します。
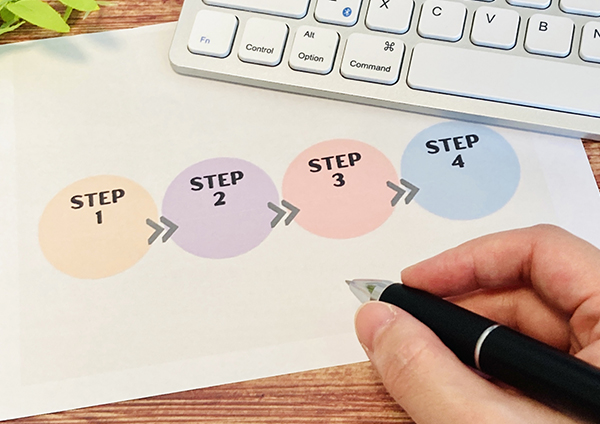
- 目標設定・管理制度導入支援
- 「目標」を組織の推進力に。従業員の主体性を引き出し、組織目標達成を力強くサポートする目標設定・管理制度(MBOなど)の導入を支援します。企業の成長戦略と連動させ、目標設定から評価までのプロセスを最適化。組織全体のパフォーマンス向上と従業員のモチベーション向上を実現します。貴社の理念に合わせた制度設計と丁寧な導入・運用支援で、目標達成を力強く後押しいたします。

- 人事評価者研修
- 人事評価者の視点とスキル向上は、公平で納得感のある評価制度運用の鍵です。評価基準の理解、観察力・評価、ジャッジメントの向上、フィードバック技術の習得支援など、評価者の「目」を養うことで、主観や偏りを防ぎ、従業員の成長を促す効果的な評価を実現。組織全体の評価レベル向上と、人材育成を促進します。
ご相談事例
ヒアリングを行うといっても、正直な意見は言わないのではないか。第三者に対して心を開くのだろうか。
傾聴という言葉があります。外部の人間が、従業員の声に耳を傾けることで、違う視点からの質問をしていきます。それは、思ってもいなかった方向からの問いかけに、新鮮な期待を抱いてくれるケースがほとんどです。経営者に対しては言えないことも、第三者には心開くことができると信じています。
数百万円かけても、運用できなければただの紙切れ。価制度は、中小企業には合わないんじゃないか。
評価制度の運用の失敗は、職務の定義づけがうまくできておらず、なおかつ評価者トレーニングができていないことが挙げられます。フレームはできていても、中身が伴っていないケースが多く見受けられます。企業の体型に合わせた評価制度の構築をしていきます。
従業員の要望もあり、よかれと思い賃金を上げました。しかし、少し経つとまた元通りになってしまいました。
賃金は衛生要因と言って、モチベーションの維持には短期的な要件であるため、いくら賃金を上げても長続きしないと言われています。もちろんマイナスばかりではありませんが、賃金よりも効果的なことが、承認であったり仕事の達成感であったりすることであると言えます。非金銭的報酬でやる気につなげていくことが大切です。
誰にリーダーを任せればいいのかわかりません。営業成績がよくても、管理者としては今一つなんです。
リーダーの多くは、成績もよく、勤務年数が長く、企業の中のこともわかる人ととらえられがちですが、リーダーは自分の業績も大切ですが、組織としての業績も求められます。そのためには、いかに部下に対して仕事を任せられるかがポイントとなるでしょう。組織のレベルアップのためにも、リーダーの選任も気にしてみてはいかがですか。
人の採用や教育という点で悩んでいます。中小企業は人を育てるのが難しくて。
PDCA ではなく、STPD サイクルであるという一節があります。
- See「事実を見ること」
- Think「事実を共有し考える」
- Plan「計画する」
- Do「実行する」
これは、ソニーの工場において培われたもので、まず物事をよく見てから計画を立てることだというのです。経営者が現実を見て判断し、適切な方向に舵を取る。人を動かすことはとても大変なことですが、お互いを知り、そして情報を共有することで、組織風土も変わり、それによってもたらされる効果も大きいと考えます。
